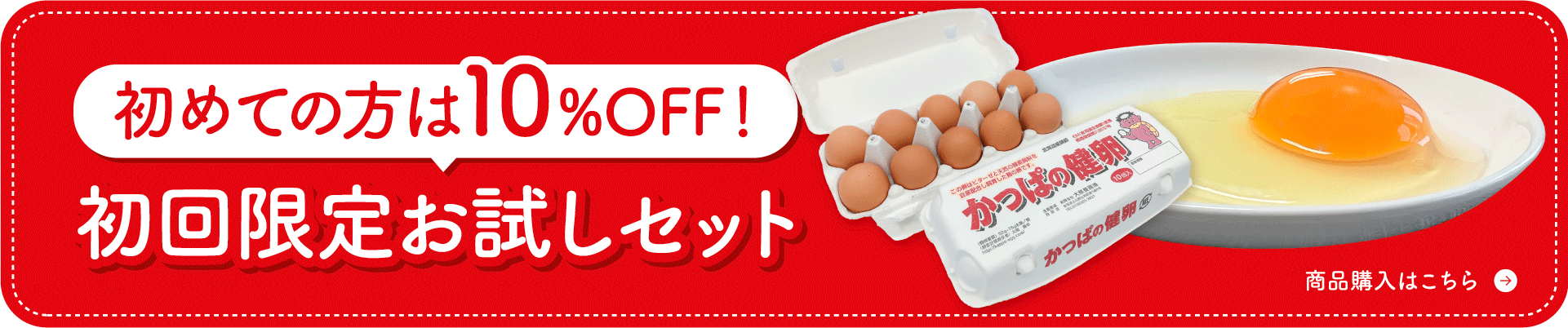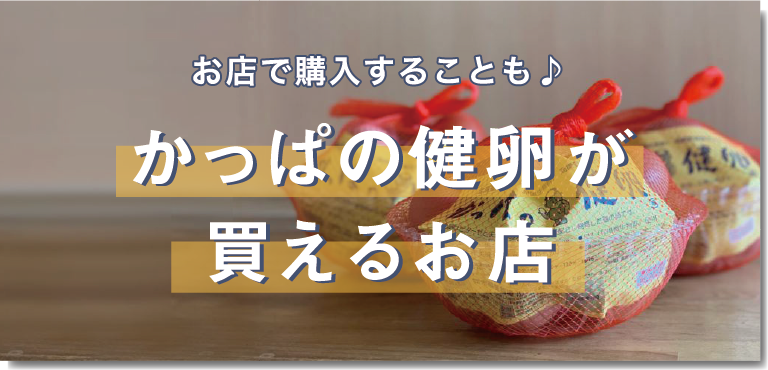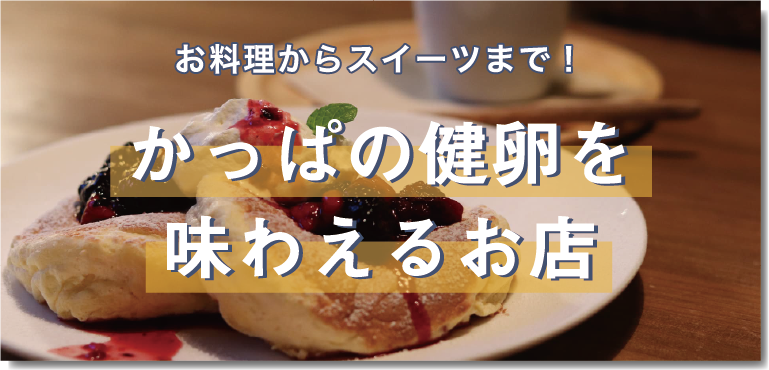離乳食の卵粥はいつから?時期別レシピ&冷凍法・時短のコツまで解説

栄養満点の卵粥は、赤ちゃんの成長に合わせて取り入れたい離乳食の定番ですよね。
今回は、「卵粥っていつからOK?」「初期と後期でどう作り分けるの?」「冷凍できるの?」
そんなママ・パパの疑問に答える記事です。
北海道比布町でブランド卵「かっぱの健卵」を生産する大熊養鶏場が、離乳食における卵粥の開始時期・月齢別の調理法・冷凍方法・嬉しい時短テクニックまで、丁寧に解説します。
毎日子育てに追われるあなたも、これを読めば、安心して離乳食に卵粥を取り入れられるようになるでしょう。ぜひ最後までご覧ください。
離乳食の卵粥はいつから食べさせていい?

赤ちゃんの発達には個人差がありますが、一般的に離乳食初期(生後5〜6ヶ月頃)から卵を取り入れることができます。ただし、最初は必ず卵黄から始めましょう。
離乳食初期(生後6ヶ月頃〜)卵粥は「卵黄から」
離乳食初期は、赤ちゃんが初めて食べ物に触れる大切な時期です。卵アレルギーのリスクを考慮し、まずは固茹でした卵の卵黄を少量(耳かき1杯程度)から与えてみましょう。
卵白にはアレルゲンが多く含まれているため、最初は避けるのが基本です。固ゆでした卵黄を湯冷ましや10倍粥に混ぜて、滑らかに潰した状態で与えます。
アレルギー症状がないか慎重に観察しながら、少しずつ量を増やしていきます。もし、皮膚の発疹、嘔吐、下痢などの症状が見られた場合は、すぐに医師に相談してください。
離乳食の卵粥は毎日あげても大丈夫?

卵は栄養価が高く、離乳食に積極的に取り入れたい食材の一つと言えます。
ここでは、「卵粥を毎日食べさせてもいいの?」といった疑問にお答えします。
毎日でもOK。ただしバランスが大切
卵粥を赤ちゃんが気に入ってくれた場合、毎日与えても基本的に問題ありません。ただし、他の食材とのバランスを考えることが重要です。
離乳食は、様々な食材から栄養を摂ることで、赤ちゃんの健やかな成長をサポートします。卵粥だけでなく、野菜や豆腐、魚など、色々な種類の食材を組み合わせて与えるように心がけましょう。
また、同じ食材ばかりを与えていると、アレルギーのリスクが高まる可能性も指摘されています。卵粥を毎日与える場合は、他の食事で違う食材を取り入れるなど、工夫するようにしましょう。
離乳食初期・中期・後期の卵粥レシピ

赤ちゃんの成長に合わせて、卵粥の作り方や卵の量、食材の形状を少しずつ変えていくことが大切です。ここでは、離乳食初期・中期・後期それぞれの時期に合わせた卵粥のレシピをご紹介します。
離乳食初期(5〜6ヶ月頃)
材料
- 10倍粥:大さじ2
- 固茹でした卵黄:1/8個
- 湯冷まし:少量
作り方
- 固茹でした卵黄を少量のお湯で溶き、滑らかにする。
- 温めた10倍粥に、1の卵黄を混ぜ合わせる。
- 赤ちゃんが食べやすいように、必要であればさらに湯冷ましで伸ばす。
ポイント
- 最初は耳かき1杯程度の卵黄から始め、様子を見ながら量を増やしていく。
- 卵黄はしっかりと加熱し、生のまま与えないように注意する。
- アレルギーの兆候がないか、注意深く観察しながら進める。
離乳食中期(7〜8ヶ月頃)
材料
- 7倍粥:大さじ3
- 固茹でした卵黄:1/4個
- だし汁または湯冷まし:少量
作り方
- 固茹でした卵黄をフォークなどで細かく潰す。
- 温めた7倍粥に、1の卵黄を混ぜ合わせる。
- パサつく場合は、だし汁または湯冷ましで食べやすい固さに調整する。
ポイント
- 卵黄の量を少しずつ増やしていく。
- 舌で潰せる程度の固さに調理する。
- 慣れてきたら、みじん切りにした野菜などを加えても良い。
離乳食後期(9〜11ヶ月頃)
材料
- 5倍粥:大さじ4
- 全卵:1/3個
- だし汁:大さじ1
- みじん切りにした野菜(ほうれん草、人参など):少量
作り方
- 卵を溶きほぐし、だし汁と混ぜ合わせる。
- 温めた5倍粥に、みじん切りにした野菜と1の卵液を加える。
- 弱火にかけ、混ぜながら卵が固まるまで加熱する。
ポイント
- 全卵を使用する際は、アレルギーに注意しながら少量から試す。
- 具材を増やして、栄養バランスを整える。
- 手づかみ食べしやすいように、少し水分を飛ばして作るのもおすすめ。
離乳食後期におすすめ!時短できる卵粥レシピ
卵アレルギーの心配も減ってくる離乳食後期になると、赤ちゃんも食べる量が増え、ママの調理の負担も大きくなりがち。そこで、電子レンジや炊飯器を活用した、簡単で時短になる卵粥レシピを2つご紹介します。

電子レンジで簡単!卵粥
材料:
- ご飯(軟飯):80g
- 水またはだし汁:100ml
- 溶き卵:1/4個
- みじん切りにした野菜(お好みで):少量
作り方:
- 耐熱容器にご飯(軟飯)、水またはだし汁、野菜を入れる。
- ふんわりとラップをかけ、電子レンジ(600W)で1分30秒〜2分加熱する。
- 一度取り出し、溶き卵を回し入れる。
- 再びラップをかけ、電子レンジで30秒〜1分加熱する。卵が固まっているか確認し、加熱が足りなければ10秒ずつ追加する。
- 全体を混ぜ合わせ、粗熱を取ってから与える。
ポイント:
- 加熱時間は、電子レンジの機種やワット数によって調整してください。
- 卵が爆発しないように、加熱しすぎに注意しましょう。
- 火を使わないので、忙しい時でも手軽に作れます。
炊飯器でまとめて作る卵粥

材料:
- 米:1/2合
- 水:適量(お粥モードの水加減に合わせる)
- 溶き卵:1個
- だしパックまたは顆粒だし:少量
- みじん切りにした野菜(お好みで):少量
作り方:
- 米を研ぎ、炊飯器のお粥モードに合わせて水加減を調整する。
- だしパックまたは顆粒だし、野菜を加えて炊飯する。
- 炊き上がったら、全体を混ぜ合わせる。
- 食べる分だけ器に取り分け、温めてから溶き卵を少量ずつ加えて混ぜ合わせる。余熱で卵がふんわりと仕上がる。
ポイント:
- 炊飯器でまとめて作れるので、数回分を一度に準備できます。
- 全量に卵を入れてしまうと傷みやすいので、食べる直前に加えるのがおすすめです。
- 野菜の種類や量を調整すれば、色々なバリエーションが楽しめます。
卵粥の冷凍・解凍方法

離乳食用に作った卵粥が余ってしまった場合や、まとめて作り置きしておきたい場合に便利なのが冷凍保存です。安全に美味しく保存するためのポイントと、解凍・再加熱のコツをご紹介します。
冷凍保存のポイント
小分けにする
1回分ずつ小分けにして冷凍するのがおすすめ。製氷皿や離乳食用の保存容器などを活用すると便利です。
ラップで密閉
小分けにした卵粥は、空気に触れないようにラップでしっかりと包み、保存袋に入れて冷凍庫へ。
急速冷凍
金属製のバットなどに乗せ、なるべく早く冷凍することで、風味や食感を損なわずに保存できます。
注意点
- 炊き上がった卵粥は、しっかりと粗熱を取ってから冷凍しましょう。温かいまま冷凍すると、品質が落ちる原因になります。
- 食べかけの卵粥は唾液がついており、雑菌が繁殖する可能性が高いため冷凍は避けてください。
- 冷凍保存した卵粥は、1週間を目安に使い切るようにしましょう。
解凍・再加熱の方法丨注意点
以下のいずれかの方法があります。
①冷蔵庫で自然解凍
冷凍した卵粥は、食べる数時間前に冷蔵庫に移して自然解凍するのが最も安全でおすすめの方法です。解凍できたら、さらに電子レンジで30秒~1分ほど温めます。
②電子レンジ解凍
急ぎの場合は、電子レンジの解凍モードを使用してもOK。ただし、加熱ムラができないよう注意し、様子を見ながら加熱しましょう。
③鍋で再加熱
凍ったままの卵粥を鍋に移し、少量のお水またはだし汁を加えて弱火で温めます。焦げ付かないように混ぜながら加熱してください。
<注意点>
再冷凍はNG
一度解凍した卵粥は、品質が劣化しやすいため、再冷凍は絶対に避けてください。
加熱後は必ず確認する
再加熱した卵粥は、加熱ムラがないか・熱すぎないか、温度を確認してから赤ちゃんに与えましょう。
栄養満点の卵粥を離乳食に活用しよう
今回は、離乳食の卵粥について、開始時期から月齢別のレシピ、そして冷凍・解凍方法、時短テクニックまで詳しく解説しました。
卵は、赤ちゃんの成長に欠かせない栄養がたっぷり詰まった食材です。初期は卵黄から始め、赤ちゃんの様子を見ながら少しずつステップアップしていきましょう。
忙しいママには、電子レンジや炊飯器を活用した時短レシピもおすすめです。また、冷凍保存を上手に活用すれば、調理の負担を減らすことができますよ。

毎日がんばってる自分と赤ちゃんのために、ちょっといい卵、使ってみませんか?
大熊養鶏場がお届けする「かっぱの健卵」は、 科学物質や余計なものを一切使わず、鶏の健康から考え抜いたこだわりの卵です。
生臭くなくて、赤ちゃんも喜ぶおいしさだから、離乳食にもぴったり。
一度食べたら、その違いがわかるはず。少しでも気になった方は、ぜひかっぱの健卵のこだわりをのぞいてみてくださいね。
かっぱの健卵の3つのこだわり